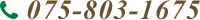山 原 條 二
合成の医薬品のみに依存しない健康づくりを考え、実践することを多方面から行っています。
しかし、合成の医薬品を服用中の会員の方々からの質問も多数いただいたので、年齢と共に医薬品による副作用の率が高くなる理由を解説します。
① 加齢と共に急性の病気だけではなく、慢性疾患を2、3併発していて服用する医薬品の数が多く医薬品相互の思わぬ作用。
② この多数の医薬品を服用することへの理解度が低い。
③ 長期間服用による肉体的変化を配慮していない。これは医薬品の消化管からの吸収が、胃腸の運動や血流量の低下によって遅くなっていることも原因の一つとして考えられます。しかしこれが重要な因子の一つとは言うほどのものではありません。
年齢と共に体の総体液量や脂肪以外の組織分が減少するために、服用した薬物が実質上高用量となって副作用が出たり、薬物は血中のアルブミンと結合して不活性の状態になっている場合が多いのです。しかし血中のアルブミンが慢性疾患では少なくなっていることも多く、作用を示す遊離型で血中に薬物が多くあり強すぎる作用、すなわち副作用となったりします。
又、体内で薬物を無毒化する代謝は肝臓で行われ、肝重量や肝血流量が低下していて代謝が遅くなったり、さらに薬物を排泄する腎臓の腎血流量が糸球体濾過力も低下します。 このように自分がどのような状態にあって合成の医薬品を服用しているのか。その薬物を服用する必要があるのか。よく専門家と相談、納得してという態度も必要です。
一つひとつ医薬品の安全性の試験は、かなり広範囲の毒性発現を予想して行われています。しかし、何種類も複合した形で服用する場合の、毒性を想定した安全性の試験は誰も行っていない点も知っておく必要があります。
何よりも合成の医薬品に依存しない日頃からの健康造り「食養生」と「適度な運動」が大切です。
本記事は認定特定非営利活動法人 天然薬用資源開発機構の承認のもと、転載しております。
天然薬用資源開発機構では自然に根差した健康造りの情報を他にもたくさん発信しております。
天然薬用資源開発機構のホームページをぜひご訪問ください。
http://www.tenshikai.or.jp/